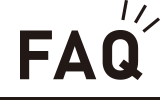

自己破産できないことがあるとは本当ですか?
 消費者金融に手を出してから10年以上になり、これまでは月末までにピンチになれば借入して、給料が出たらその分をきちんと完済して消費者金融で作ったカードを有意義に利用していました。
消費者金融に手を出してから10年以上になり、これまでは月末までにピンチになれば借入して、給料が出たらその分をきちんと完済して消費者金融で作ったカードを有意義に利用していました。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行したときにしばらくボーナスがでない月が続き、その前にちょうど家電と家具を買い替えするためにローンを組んでしまっていて、さらに自動車のローンもあったので、それらの分の支払いができなくてまとまった金額を借りてしまい、給料だけでは完済できずにお金を借りたままにしてしまいました。
その後コロナも終息してボーナスももらえるようになりましたが、その間に他の消費者金融やクレジットカードのキャッシングにも手を出してしまい多重債務者になりました。
それでも何とか最低限の返済はしてきましたが、ついに限界を迎えたようです。もう自己破産するしかないと思い信頼できる友人に相談すると、自己破産できないこともあるから早めに弁護士に相談に行くように言われました。
過去に返済の滞納などお金に関する事故は起こしたことはないのですが、それでも自己破産できないことはあるのでしょうか?自己破産できない場合はどうすればいいのでしょうか?
![]()

自己破産は誰でもできるわけではありません
自己破産とは、裁判所から免責許可決定を得ることで合法的に債務の支払いを免れることができる強力な借金解決方法です。
抱えていた多額の債務を0にできる強力な効果がある分、誰でも簡単に実行できると社会一般のお金の貸し借りのシステムが乱れてしまうため、自己破産にはそれをするための要件が定められています。自己破産ができない理由は主に3つあります。
一つ目は支払いが完全に不能ではなく、債務が支払える状態を判断されたときです。債務者が支払不能かどうかは,裁判所が判断します。
支払い不能の定義については,破産法2条11項に「債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と規定されています。
裁判所が客観的な立場で債務者の状況を確認し,本当に返済できないか否かを判断します。債務の額や収入について明確な基準はありませんが、資産総額や生活状況、家族構成、債務を負担した経緯などを総合的に確認し、支払い能力を判断します。
自己破産できない二つ目の理由には、免責が不許可となるケースに当てはまることが挙げられます。
借金を作った原因や自己破産手続に関連して債務者の言動に問題があるような場合は,裁判所が免責を不許可にすることがあります。これを免責不許可事由と呼びます。
ギャンブルや贅沢品を購入して借金を作った場合などは、免責不許可事由に当たる可能性が高いです。自己破産をするにあたり意図的に財産を隠したり減少されたりすることも免責不許可事由に当たります。
他にも、特定の債権者だけを優先して借金を弁済する、自己破産をする前提でお金を借りる、裁判所に嘘をついたりすることも免責不許可事由に当たります。また、過去に自己破産をしていて前回の免責から7年経っていないことも免責不許可事由となります。
ただし、免責不許可事由があるケースでも、裁判所の裁量により免責を認めるケースも多いです。借金をしたことに真摯に反省して生活を立て直すことに意欲を持ち、裁判所に対して誠実で嘘のない態度で挑むことが大切です。
自己破産ができない三つ目の理由は、税金などの非免責債権が債務の中心であることです。
非免責債権には,税金や社会保険料以外に、罰金、婚姻費用や養育費、従業員に対する賃金、交通事故による損害賠償金などがあります。このようなものが債務の中心である場合は、自己破産が認められない可能性が高いです。
自己破産ができない場合でも、「任意整理」「個人再生」などの他の債務整理で借金の負担を軽減させることが可能です。
任意整理はお金を借りている債権者と交渉し,利息の免除や返済計画の見直しなどに同意してもらう手続きです。借金の額が比較的少ない人に向いています。
自己破産とは違い裁判所を通さないため,面倒な手続きや多くの書類の提出も必要ありません。家族などに知られずに解決できることも多いです。対象となる債務を選べることから、特定の貸金業者の借金のみを軽減させることも可能です。
個人再生は自己破産と同じく裁判所を介す手続きですが、借金の総額を5分の1程度に大幅に減額できます。最大で10分の1程度減らすことも可能です。個人再生では,自己破産のように財産を手放す必要もありません。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」という制度を利用することで住宅ローンを支払い中の自宅にそのまま住み続けられるということです。
注意すべきことは,債務が完全になくなるわけではなく,圧縮後の債務は原則3年(最大で5年)で支払わなければならないことです。
抱えていた多額の債務を0にできる強力な効果がある分、誰でも簡単に実行できると社会一般のお金の貸し借りのシステムが乱れてしまうため、自己破産にはそれをするための要件が定められています。自己破産ができない理由は主に3つあります。
一つ目は支払いが完全に不能ではなく、債務が支払える状態を判断されたときです。債務者が支払不能かどうかは,裁判所が判断します。
支払い不能の定義については,破産法2条11項に「債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と規定されています。
裁判所が客観的な立場で債務者の状況を確認し,本当に返済できないか否かを判断します。債務の額や収入について明確な基準はありませんが、資産総額や生活状況、家族構成、債務を負担した経緯などを総合的に確認し、支払い能力を判断します。
自己破産できない二つ目の理由には、免責が不許可となるケースに当てはまることが挙げられます。
借金を作った原因や自己破産手続に関連して債務者の言動に問題があるような場合は,裁判所が免責を不許可にすることがあります。これを免責不許可事由と呼びます。
ギャンブルや贅沢品を購入して借金を作った場合などは、免責不許可事由に当たる可能性が高いです。自己破産をするにあたり意図的に財産を隠したり減少されたりすることも免責不許可事由に当たります。
他にも、特定の債権者だけを優先して借金を弁済する、自己破産をする前提でお金を借りる、裁判所に嘘をついたりすることも免責不許可事由に当たります。また、過去に自己破産をしていて前回の免責から7年経っていないことも免責不許可事由となります。
ただし、免責不許可事由があるケースでも、裁判所の裁量により免責を認めるケースも多いです。借金をしたことに真摯に反省して生活を立て直すことに意欲を持ち、裁判所に対して誠実で嘘のない態度で挑むことが大切です。
自己破産ができない三つ目の理由は、税金などの非免責債権が債務の中心であることです。
非免責債権には,税金や社会保険料以外に、罰金、婚姻費用や養育費、従業員に対する賃金、交通事故による損害賠償金などがあります。このようなものが債務の中心である場合は、自己破産が認められない可能性が高いです。
自己破産ができない場合でも、「任意整理」「個人再生」などの他の債務整理で借金の負担を軽減させることが可能です。
任意整理はお金を借りている債権者と交渉し,利息の免除や返済計画の見直しなどに同意してもらう手続きです。借金の額が比較的少ない人に向いています。
自己破産とは違い裁判所を通さないため,面倒な手続きや多くの書類の提出も必要ありません。家族などに知られずに解決できることも多いです。対象となる債務を選べることから、特定の貸金業者の借金のみを軽減させることも可能です。
個人再生は自己破産と同じく裁判所を介す手続きですが、借金の総額を5分の1程度に大幅に減額できます。最大で10分の1程度減らすことも可能です。個人再生では,自己破産のように財産を手放す必要もありません。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」という制度を利用することで住宅ローンを支払い中の自宅にそのまま住み続けられるということです。
注意すべきことは,債務が完全になくなるわけではなく,圧縮後の債務は原則3年(最大で5年)で支払わなければならないことです。

Copyright(C) 横浜SIA法律事務所 All Right Reserved.








